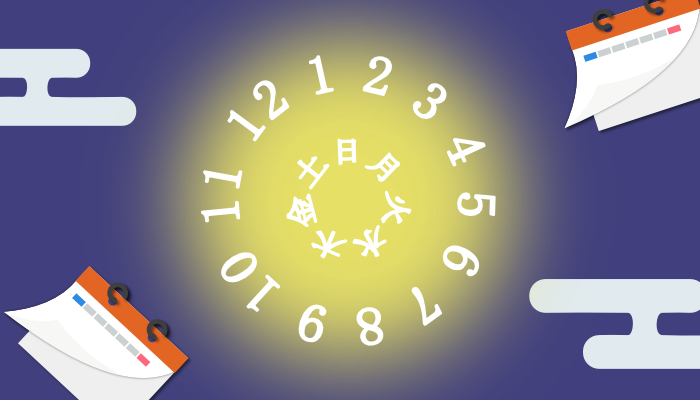六曜
六曜*ろくよう、りくようとは、もともと中国で「時間」を区切ものとして使われていたもので、鎌倉時代末期ごろに日本に伝わったとされ、当初は、現在使われている「月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜」の七曜のようなものだったと言われている。
その後、江戸時代の終わり頃から、現在のように日の吉凶を占うものへと変化したが、その根拠は不明。
六曜のしくみ
「先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口」の順番で毎日繰り返し、旧暦の月が変わるときに、その連続性を一度断ち、また新しい月の1日から、所定の決められた星から再びスタートする。
旧暦の1月1日・7月1日
先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 →
旧暦の2月1日・8月1日
友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 →
友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 →
旧暦の3月1日・9月1日
先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 → 先負 →
旧暦の4月1日・10月1日
仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 →
旧暦の5月1日・11月1日
大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 →
旧暦の6月1日・12月1日
赤口 → 先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 →
先勝
先勝*せんしょう、さきがち、せんかちとは、何事も早くことを済ませてしまうことが良いとされる日のこと。
先んずればすなわち勝つ
急ぎの用事
引っ越し
訴訟
お参り
結納・入籍・結婚
など
告別式
友引
友引*ともびき、ゆういんとは、勝負の決着がつかず、良くも悪くもないとされる日のこと。
友引に葬儀を行うと、「亡くなった人が友を呼び寄せる」といった迷信があり、友引の日は葬祭関連業や火葬場が休業となっていることがある。
友を引き寄せる
引っ越し
納車・契約
結納・入籍・結婚
など
葬式・告別式
通夜・法事・お別れ会
お見舞い
先負
先負*せんぷ、せんふ、せんまけ、さきまけとは、何事も控えめに静かに過ごすのが良いとされる日のこと。
先んずればすなわち負ける
引っ越し
納車・契約
結納・入籍・結婚
お宮参り・合格祈願
葬式・法事
など
宝くじの購入
争い事・勝負事
仏滅
仏滅*ぶつめつとは、すべての物事に凶とされ、何事も控えたほうが良い一日とされる日のこと。
物が滅する
宝くじの購入
お参り
お守りを買う・返納する
葬式・告別式・法事
など
引っ越し
納車
開業・開店
大安
大安*たいあんとは、六曜の中で最も良い日とされ、すべてにおいて何をしても上手くいき成功するとされる日のこと。
ただし、建築の大凶日ある「三隣亡*さんりんぼう」や何事も成就しないとされる「不成就日*ふじょうじゅび」と重なる日は、三隣亡や不成就日の影響が優先されるため、大安であっても関係なく悪い日となるようだ。
大いに安し
財布を買う・使い始める
仕事始め
開店・開業
銀行口座開設
宝くじの購入
出資
納車
商談・契約・勝負事
結納・入籍・結婚
お宮参り
など
葬式
赤口
赤口*しゃっこう、じゃっこう、しゃっく、じゃっく、せきぐちとは、古くから魔物がいると考えられている「丑寅の刻*午前2時~4時」の時間帯に当てはめられていました。このことから、赤い口の鬼が災いをもたらす日とされています。
牛の刻*11~13時の2時間は鬼が休むため、この時間帯のみ吉です。何かを行うならこの時間が良いとされています。
すべてが消滅する
お宮参り
葬式・告別式・法事
など
お見舞い
引っ越し
開店・開業
納車
商談・契約・勝負事
入籍・結婚式