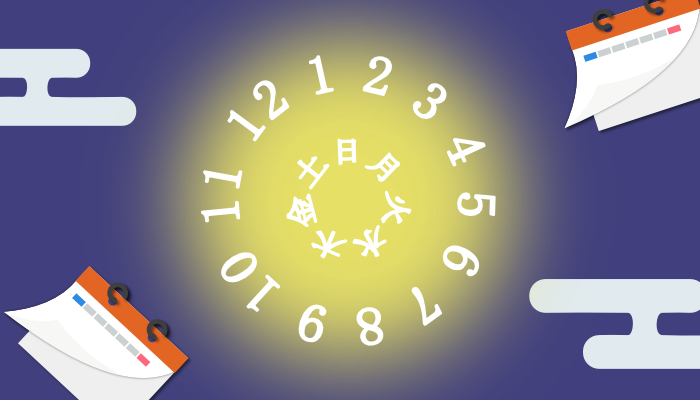飛鳥時代
飛鳥時代*あすかじだいの元号*年号は、645年に日本の最初の元号として「大化」が用いられてから「和銅」までの「6」の元号が存在している。
大化 たいか
皇極天皇4年6月19日
ユリウス暦:645年7月17日
大化6年2月15日
650年3月22日
6年
第36代 孝徳天皇 こうとくてんのう
在位
皇極天皇4年6月14日-白雉5年10月10日
645年7月12日-654年11月24日
天下安寧*てんかあんねい
/ 世の中が穏やかで安定していること
政化敷行*
/ これから朝廷が政治を取り仕切ること
「日本書紀」巻25 孝徳天皇
日本書紀*にほんしょきとは、日本最古の歴史書のひとつ。
改天豊財重日足姫天皇四年為大化元年
天豐財重日*あめとよたからいかしひ 足姬天皇*たらしひめのすめらみこと
/ 皇極天皇(こうぎょくてんのう)の和風諡号(わふうしごう)の4年を「大化元年」に改める
「書経(尚書)」周書 大誥 第35
書経*しょきょうとは、古代中国の経書。
肆予大化誘我友邦君
故に予*われは大いに我が友邦*ゆうほう
/ 互いに親しくしている国の君主たちを誘い導く
「漢書」巻56
漢書*かんじょとは、古代中国王朝 前漢*ぜんかんのことを記した歴史書。
古者修教訓之官務以徳善化民、民已大化之後天下常亡一人之獄矣
古代人は徳を持って民を教え育成する公務を実践していた、人々が偉大になった後、世界は常に一人の人間が死ぬための牢獄になるでしょう
「宋書」巻20
宋書*そうじょとは、古代中国の南北朝時代の南朝の国 宋*そうのことを記した歴史書。
神武鷹揚、大化咸煕
白雉 はくち
白雉 びゃくち
白雉 しらきぎす
大化6年2月15日
650年3月22日
白雉5年12月30日
655年2月11日
5年
第36代 孝徳天皇 こうとくてんのう
在位
皇極天皇4年6月14日-白雉5年10月10日
645年7月12日-654年11月24日
穴戸国*あなとのくに
/ 山口県西部の国司 草壁醜経*くさかべのしこぶが「白いキジ*白雉」を献上*けんじょう
/ 主君や貴人に物を差し上げることした祥瑞*しょうずい
/ めでたいことが起こるという前兆による改元
由来
良いことが起こる前兆を表す鳥とされる「白いキジ」が献上されたことに由来する
「漢書」巻12 平帝紀
元始元年正月越裳氏、重訳献白雉
「論衡」巻8 儒増篇
論衡*ろんこうとは、古代中国の後漢時代の思想家 王充*おう じゅうが著した思想書。
周時天下太平,越裳獻白雉,倭人貢鬯草
古代中国の王朝 西周*せいしゅうの第2代の王 成王*せいおうの時代に天下太平の象徴として、越裳*えつしょう
/ 中国南部の民族名称と思われるが白雉を獻上し、倭人*わじん
/ 日本人が鬯草*ちょうそう
/ 暢草を貢いだ
-
-
-
-
第37代女帝 斉明天皇 さいめいてんのう
在位
斉明天皇元年1月3日-斉明天皇7年7月24日
655年2月14日-661年8月24日
孝徳天皇の崩御*ほうぎょに伴い、皇極天皇*こうぎょくてんのうが重祚*ちょうそして、斉明天皇となり元号を定めなかった
-
-
-
-
-
第38代 天智天皇 てんじてんのう
在位
天智天皇7年1月3日-天智天皇10年12月3日
668年2月20日-672年1月7日
重祚*ちょうそした斉明天皇以降元号は定めらていない
-
-
-
-
-
第39代 弘文天皇 こうぶんてんのう
在位
天智天皇10年12月5日-天武天皇元年7月23日
672年1月9日-672年8月21日
重祚*ちょうそした斉明天皇以降元号は定めらていない
-
朱鳥 しゅちょう
朱鳥 すちょう
朱鳥 あかみとり
天武天皇15年7月20日
686年8月14日
朱鳥元年閏12月30日
687年2月17日
6か月
第40代 天武天皇 てんむてんのう
在位
天武天皇2年2月27日-朱鳥元年9月9日
673年3月20日-686年10月1日
天武天皇の病気平癒*びょうきへいゆを祈願した改元と思われる
由来
中国の「四神*ししん」のひとつである「朱鳥」は、良いことが起こる前兆を表す鳥と考えられており、天武天皇に「赤い雉*朱鳥」が献上*けんじょうされたことを吉兆としたことに由来する
「礼記」曲礼
礼記*らいきとは、古代中国の経書。
行前朱鳥而後玄武、左青龍而右白虎
列の先頭に朱鳥、その後ろに玄武、左側に青龍、右側に白虎がいる
「史記」天官書
史記*しきとは、中国最初の歴史書。
東宮蒼龍、南宮朱鳥、西宮咸池、北宮玄武
東宮に青龍、南宮に朱鳥、西宮に白虎、北宮に玄武
-
-
-
-
第41代女帝 持統天皇 じとうてんのう
在位
持統天皇4年1月1日-持統天皇11年8月1日
690年2月14日-697年8月22日
天武天皇の崩御*ほうぎょした翌年から元号を定めなかった
-
-
-
-
-
第42代 文武天皇 もんむてんのう
在位
文武天皇元年8月1日-慶雲4年6月15日
697年8月22日-707年7月18日
天武天皇の崩御*ほうぎょした翌年から元号は定められていない
-
大宝 たいほう
大宝 だいほう
文武天皇5年3月21日
701年5月3日
大宝4年5月10日
704年6月16日
4年
第42代 文武天皇 もんむてんのう
在位
文武天皇元年8月1日-慶雲4年6月15日
697年8月22日-707年7月18日
対馬国*つしまのくに
/ 長崎県対馬で国内で初め産出されたとされる「金」が献上*けんじょうされた祥瑞*しょうずい
による改元
ただし、献上された金は、対馬国で産出されたものではなかったという説もある
「易経(周易)」繋辞下
易経*えききょうとは、古代中国の儒教*じゅきょうの経典。
天地之大徳曰生、聖人之大宝曰位
天地の大いなる徳を生いい、聖人の大いなる宝を位いう
慶雲 けいうん
慶雲 きょううん
大宝4年5月10日
704年6月16日
慶雲5年1月11日
708年2月7日
5年
第42代 文武天皇 もんむてんのう
在位
文武天皇元年8月1日-慶雲4年6月15日
697年8月22日-707年7月18日
第43代女帝 元明天皇 げんめいてんのう
在位
慶雲4年7月17日-和銅8年9月2日
707年8月18日-715年10月3日
宮中の西楼*せいろう
/ 西側にある高く造った殿舎の上にめでたいことが起こる前兆とされる虹色の雲が現れた祥瑞*しょうずいによる改元
由来
めでたいことが起こる前兆とされる虹色の雲「慶雲」が現れたことに由来する
「文選」巻6
文選*もんぜんとは、古代中国の詩文集。
朝想慶雲興、夕遅白日移
朝はめでたい雲が生じると想うが、夕方には太陽が遠ざかるだろう
「晋書」巻54 陸雲伝
晋書*しんじょとは、古代中国王朝「晋*しん」のことを記した歴史書。
天網広羅、慶雲興以招龍
和銅 わどう
慶雲5年1月11日
708年2月7日
和銅8年9月2日
715年10月3日
8年
第43代女帝 元明天皇 げんめいてんのう
在位
慶雲4年7月17日-和銅8年9月2日
707年8月18日-715年10月3日
武蔵国秩父郡*埼玉県秩父市で採掘された「自然銅」が献上*けんじょうされた祥瑞*しょうずいによる改元
「礼記」第6篇 月令 孟春
是月也 天氣下降 地氣上騰 天地和同 草木萌動
この月や 天気は下降し 動植物の成育を助ける大地の精気は高く上がり 天と地は調和し 草木が芽吹き始める