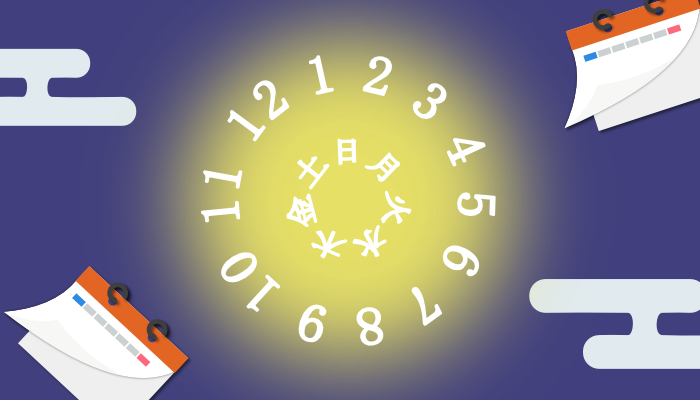新暦とは
新暦*しんれきとは、現在、日本を含め多くの国で使われている暦「グレゴリオ暦*太陽暦」のことで、太陽の動きに合わせて作られたもの。
グレゴリオ暦とは、ローマ教皇 グレゴリオ13世*Pope Gregory XIIIによって、従来のユリウス暦を廃して、1582年10月15日 金曜日から新たに制定された暦のこと。
地球が太陽の周りを 1周するのにかかる日数は「365.2422日」で、きりの良い数にはならないため、毎年の余りとなる「0.2422日分」の誤差を修正するために、4で割り切れる年を「閏年*うるうどし
/ 1年=366日」に、100で割り切れる年を「平年*1年=365日」としたもの。
よって、暦のズレを調整するために、暦に設けられた4年に一度訪れる日を「閏日*うるうび」という。
日本で正式に使用されるようになったのは明治時代で、旧暦の「1873年*明治5年 12月3日」を新暦の「1873年*明治6年 1月1日」と定められ、新しく採用された暦を「新暦」、それまでの暦を「旧暦」と呼ぶようになった。
旧暦とは
旧暦*きゅうれきとは、明治以前に使われていた暦「太陰太陽暦*たいいんたいようれき
/ 太陰暦、陰暦」のことで、暦を月の満ち欠けに合わせてつくられたもの。
新月が満ちて満月になり、また欠けて次の新月になるまでを「1か月」と考え、天体の月が地球をまわる周期の長さは約 29.5日になるので、1か月を29日とする月を「小の月」、1か月を30日とする月を「大の月」と表し、1年を354日*29.5日×12ヵ月=354日としている。
新暦では、1年を365日としているため、旧暦と比べると11日間少なくなり、ズレが生じている。そこで太陰太陽暦では、2~3年に1度は閏月*うるうづきを設けて13ヶ月ある年をつくることでズレを解消していたとされる。
日本では、古代中国から百済*くだらを通じて日本に伝えられた「太陰太陽暦*中国歴」をもとに、飛鳥時代の604年*推古12年に日本最初の暦が作られたと伝えられている。