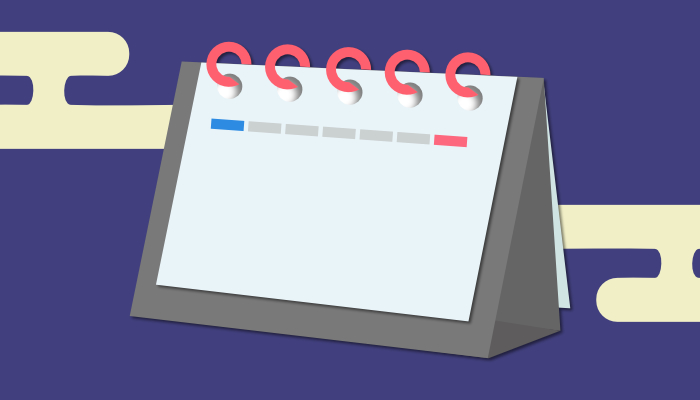室町時代
応永 おうえい
明徳5年7月5日
1394年8月2日
応永35年4月27日
1428年6月10日
35年
第100代 後小松天皇 ごこまつてんのう
在位
永徳2年4月11日-応永19年8月29日
1382年5月24日-1412年10月5日
第101代 称光天皇 しょうこうてんのう
在位
応永19年8月29日-正長元年7月20日
1412年10月5日-1428年8月30日
天然痘(てんねんとう / 疱瘡)の流行
干魃(かんばつ / 農作物に必要な雨が長い間降らず作物が不作)など
「唐会要(とうかいよう)」
久応称之、永有天下
正長 しょうちょう
応永35年4月27日
1428年6月10日
正長2年9月5日
1429年10月3日
2年
第101代 称光天皇 しょうこうてんのう
在位
応永19年8月29日-正長元年7月20日
1412年10月5日-1428年8月30日
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
後小松天皇からの譲位を受けて、第一皇子である躬仁親王(みひとしんのう)が践祚し、称光天皇となったことによる改元
「礼記」正義
在位之君子、威儀不差忒、可以正長是四方之国
永享 えいきょう
正長2年9月5日
1429年10月3日
永享13年2月17日
1441年3月10日
13年
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
称光天皇の崩御に伴い、践祚前に後小松天皇の猶子(ゆうし / 実親子ではない二者が親子関係を結んだときの子)になっていた彦仁親王(ひこひとしんのう)が践祚し、後二条天皇となったことによる改元
「後漢書」
後漢書(ごかんじょ)とは、古代中国王朝「後漢(ごかん)」のことを記した歴史書。
能立魏々之功、伝于子孫、永享無窮之祚
嘉吉 かきつ
嘉吉 かきち
永享13年2月17日
1441年3月10日
嘉吉4年2月5日
1444年2月23日
4年
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
辛酉革命(しんゆうかくめい / 60年に一度くる「辛酉」の年に起こるとされる革命を避けるため)
「易経(周易)」随卦 象上伝
孚于嘉吉、位正中也
文安 ぶんあん
文安 ふんあん
嘉吉4年2月5日
1444年2月23日
文安6年7月28日
1449年8月16日
6年
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
甲子革令(かっしかくめい / 60年に一度くる「甲子」の年に起こるとされる革命を避けるため)
「書経(尚書)」堯典
放勲欽明、文思安安
「晋書」巻58 周札伝
晋書(しんじょ)とは、古代中国王朝「晋(しん)」のことを記した歴史書。
尊文安漢社稷
宝徳 ほうとく
文安6年7月28日
1449年8月16日
宝徳4年7月25日
1452年8月10日
4年
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
水害
地震
疾疫(しつえき / 悪性の流行病)
飢饉(ききん / 作物の不作により人々がうえ苦しむこと)
「旧唐書」巻23 礼楽
朕宝三徳、曰慈倹謙
享徳 きょうとく
宝徳4年7月25日
1452年8月10日
享徳4年7月25日
1455年9月6日
4年
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
三合の厄(さんごうのやく / 暦の上で一年に大歳・太陰・客気の三神が合することで大凶とし、この年は天災、兵乱などが多いとすることから「三合の厄」を避けるため)
天然痘(てんねんとう / 疱瘡)の流行
「書経(尚書)」周書 微子 之命
世世享徳、万邦作式
康正 こうしょう
享徳4年7月25日
1455年9月6日
康正3年9月28日
1457年10月16日
3年
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
戦乱
「史記」巻38
平康正直
「書経(尚書)」洪範
平康正直
長禄 ちょうろく
康正3年9月28日
1457年10月16日
長禄4年12月21日
1461年2月1日
4年
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
炎旱(えんかん / 日照り)
「韓非子」巻6 解老
韓非子(かんぴし)とは、古代中国の戦国時代の思想家 韓非(かんぴ)が思想書。
其建生也長、持禄也久
寛正 かんしょう
長禄4年12月21日
1461年2月1日
寛正7年2月28日
1466年3月14日
7年
第102代 後花園天皇 ごはなぞのてんのう
在位
正長元年7月28日-寛正5年7月19日
1428年9月7日-1464年8月21日
第103代 後土御門天皇 ごつちみかどてんのう
在位
寛正5年7月19日-明応9年9月29日
1464年8月21日-1500年10月21日
飢饉(ききん / 作物の不作により人々がうえ苦しむこと)
「孔子家語」
孔子家語(こうしけご)古代中国の思想家 孔子の言行、逸話を集録した書物。
外寛而内正
文正 ぶんしょう
寛正7年2月28日
1466年3月14日
文正2年3月5日
1467年4月9日
2年
第103代 後土御門天皇 ごつちみかどてんのう
在位
寛正5年7月19日-明応9年9月29日
1464年8月21日-1500年10月21日
後花園天皇からの譲位を受けて、第一皇子である成仁親王(ふさひとしんのう)が践祚し、後土御門天皇となったことによる改元
「荀子」巻5 王制
荀子(じゅんし)とは、古代中国の戦国時代の儒学思想家 荀子が著した思想書。
積文学、正身行
文献を積み上げ、正しい行いをする
応仁 おうにん
文正2年3月5日
1467年4月9日
応仁3年4月28日
1469年6月8日
3年
第103代 後土御門天皇 ごつちみかどてんのう
在位
寛正5年7月19日-明応9年9月29日
1464年8月21日-1500年10月21日
戦乱
天災地変(てんさいちへん / 自然界の変動によって起こる災害や異変)
「維城典訓」
維城典訓(いじょうてんくん)とは、中国史上唯一の女帝 則天武后(そくてんぶこう)が編纂(へんさい)させた書物。
仁之感物、物之応仁、若影随形、猶声致響
文明 ぶんめい
応仁3年4月28日
1469年6月8日
文明19年7月20日
1487年8月9日
19年
第103代 後土御門天皇 ごつちみかどてんのう
在位
寛正5年7月19日-明応9年9月29日
1464年8月21日-1500年10月21日
戦乱(せんらん / 応仁の乱)
天災地変(てんさいちへん / 自然界の変動によって起こる災害や異変)
「易経(周易)」同人卦
文明以健、中正而応、君子正也
長享 ちょうきょう
文明19年7月20日
1487年8月9日
長享3年8月21日
1489年9月16日
3年
第103代 後土御門天皇 ごつちみかどてんのう
在位
寛正5年7月19日-明応9年9月29日
1464年8月21日-1500年10月21日
外宮炎上
戦乱
疾疫(しつえき / 悪性の流行病)などによる改元
「文選」巻9
喜得全功、長享其福
延徳 えんとく
長享3年8月21日
1489年9月16日
延徳4年7月19日
1492年8月12日
4年
第103代 後土御門天皇 ごつちみかどてんのう
在位
寛正5年7月19日-明応9年9月29日
1464年8月21日-1500年10月21日
天変(てんぺん / 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変)
疾疫(しつえき / 悪性の流行病)
「孟子」
孟子(もうし)とは、古代中国の戦国時代の儒学思想家 孟子が著した思想書。
開延道徳
明応 めいおう
延徳4年7月19日
1492年8月12日
明応10年2月29日
1501年3月18日
10年
第103代 後土御門天皇 ごつちみかどてんのう
在位
寛正5年7月19日-明応9年9月29日
1464年8月21日-1500年10月21日
第104代 後柏原天皇 ごかしはらてんのう
在位
明応9年10月25日-大永6年4月7日
1500年11月16日-1526年5月18日
疾疫(しつえき / 悪性の流行病)など
「文選」巻10
徳行修明、皆応受多福、保中又子孫
「易経(周易)」大有卦
其徳剛健而文明、応乎天而時行
文亀 ぶんき
明応10年2月29日
1501年3月18日
文亀4年2月30日
1504年3月16日
4年
第104代 後柏原天皇 ごかしはらてんのう
在位
明応9年10月25日-大永6年4月7日
1500年11月16日-1526年5月18日
後土御門天皇の崩御に伴い、第一皇子である勝仁親王(かつひとしんのう)がで践祚し、後柏原天皇となったことによる改元
「爾雅」巻10 釈魚
爾雅(じが)とは、中国最古の漢字を分類した辞典。
一曰神亀、二曰霊亀、三曰摂亀、四曰宝亀、五曰文亀
一つ目は神亀、二つ目は霊亀、三つ目は摂亀、四つ目は宝亀、五つ目は文亀
永正 えいしょう
文亀4年2月30日
1504年3月16日
永正18年8月23日
1521年9月23日
18年
第104代 後柏原天皇 ごかしはらてんのう
在位
明応9年10月25日-大永6年4月7日
1500年11月16日-1526年5月18日
辛酉革命(しんゆうかくめい / 60年に一度くる「辛酉」の年に起こるとされる革命を避けるため)
「易経(周易)」
永正其道、咸受吉化、徳弘(施)四海、能継天道
大永 たいえい
大永 だいえい
永正18年8月23日
1521年9月23日
大永8年8月20日
1528年9月3日
8年
第104代 後柏原天皇 ごかしはらてんのう
在位
明応9年10月25日-大永6年4月7日
1500年11月16日-1526年5月18日
第105代 後奈良天皇 ごならてんのう
在位
大永6年4月29日-弘治3年9月5日
1526年6月9日-1557年9月27日
天変(てんぺん / 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変)
天災地変(てんさいちへん / 自然界の変動によって起こる災害や異変)
戦乱
「通典」
通典(つてん)とは、古代中国王朝「唐(とう)」の歴史家 杜佑(とゆう)が書いた、唐代に至るまでの古代中国の政治や法令制度の沿革とその変遷を綴った政書。
庶務至微、至密、其大則以永業
享禄 きょうろく
大永8年8月20日
1528年9月3日
享禄5年7月29日
1532年8月29日
5年
第105代 後奈良天皇 ごならてんのう
在位
大永6年4月29日-弘治3年9月5日
1526年6月9日-1557年9月27日
後柏原天皇の崩御に伴い、第二皇子である知仁親王(ともひとしんのう)が践祚し、後奈良天皇となったことによる改元
「易経(周易)」大畜卦彖程氏伝注
居天位、享天禄也
天文 てんぶん
天文 てんもん
享禄5年7月29日
1532年8月29日
天文24年10月23日
1555年11月7日
24年
第105代 後奈良天皇 ごならてんのう
在位
大永6年4月29日-弘治3年9月5日
1526年6月9日-1557年9月27日
戦乱など
「書経(尚書)」舜典 以斉七政 注
舜察天文、斉七政
弘治 こうじ
弘治 こうぢ
天文24年10月23日
1555年11月7日
弘治4年2月28日
1558年3月18日
4年
第105代 後奈良天皇 ごならてんのう
在位
大永6年4月29日-弘治3年9月5日
1526年6月9日-1557年9月27日
106代 正親町天皇 おおぎまちてんのう
在位
弘治3年10月27日-天正14年11月7日
1557年11月17日-1586年12月17日
戦乱など
「北斉書」
北斉書(ほくせいしょ)とは、古代中国の南北朝時代の北朝の国「東魏(とうぎ)」と「北斉(ほくせい)」のことを記した歴史書。
祇承宝命、志弘治体
永禄 えいろく
弘治4年2月28日
1558年3月18日
永禄13年4月23日
1570年5月27日
13年
106代 正親町天皇 おおぎまちてんのう
在位
弘治3年10月27日-天正14年11月7日
1557年11月17日-1586年12月17日
後奈良天皇の崩御に伴い、第一皇子である方仁親王(みちひとしんのう)が践祚し、正親町天皇となったことによる改元
「群書治要」巻26
群書治要(ぐんしょちよう)とは、古代中国の唐時代の書物。
能保世持家、永全福禄者也
世界を守り家族を守り、永遠に祝福される人なり
元亀 げんき
永禄13年4月23日
1570年5月27日
元亀4年7月28日
1573年8月25日
4年
106代 正親町天皇 おおぎまちてんのう
在位
弘治3年10月27日-天正14年11月7日
1557年11月17日-1586年12月17日
戦乱など
「詩経」魯頌泮水篇
詩経(しきょう )とは、古代中国の思想家 孔子(こうし)が編んだ(編集した)とされる中国最古の詩集。
憬彼淮夷、来献其琛、元亀象歯大賂南金
「文選」巻1 蜀都賦
元亀水処、潜竜蟠於沮沢、応鳴鼓而興雨
安土桃山時代
天正 てんしょう
元亀4年7月28日
ユリウス暦:1573年8月25日
天正20年12月8日
グレゴリオ暦:1593年1月10日
20年
106代 正親町天皇 おおぎまちてんのう
在位
弘治3年10月27日-天正14年11月7日
1557年11月17日-1586年12月17日
第107代 後陽成天皇 ごようぜいてんのう
在位
天正14年11月7日-慶長16年3月27日
1586年12月17日-1611年5月9日
戦乱など
「文選」巻2 藉田賦
君以下為基、民以食為天、正其末者端其本、善其後者慎其先
「老子」第45章
老子(ろうし)とは、古代中国の春秋時代の思想家 老子が書いたと伝えられる書物。
清静者為天下正
清らかで静かな者こそが、天下の正(おさ)となる
文禄 ぶんろく
天正20年12月8日
1593年1月10日
文禄5年10月27日
1596年12月16日
5年
第107代 後陽成天皇 ごようぜいてんのう
在位
天正14年11月7日-慶長16年3月27日
1586年12月17日-1611年5月9日
正親町天皇からの譲位を受けて、孫である和仁親王(かずひとしんのう)が践祚し、後陽成天皇となったことによる改元
「通典」職官・禄秩 注
通典(つてん)とは、古代中国王朝「唐(とう)」の歴史家 杜佑(とゆう)が書いた、唐代に至るまでの古代中国の政治や法令制度の沿革とその変遷を綴った政書。
凡京文武官、毎歳給禄
慶長 けいちょう
慶長 きょうちょう
文禄5年10月27日
1596年12月16日
慶長20年7月13日
1615年9月5日
20年
第107代 後陽成天皇 ごようぜいてんのう
在位
天正14年11月7日-慶長16年3月27日
1586年12月17日-1611年5月9日
第108代 後水尾天皇 ごみずのおてんのう
在位
慶長16年3月27日-寛永6年11月8日
1611年5月9日-1629年12月22日
慶長伏見地震
天変地妖(てんぺんちよう / 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異)
「毛詩注疏(もうしちゅうそ))」
文王功徳深厚、故福慶延長也
文王の功徳はとても深くて厚い、故に良いことがいつまでも続くなり