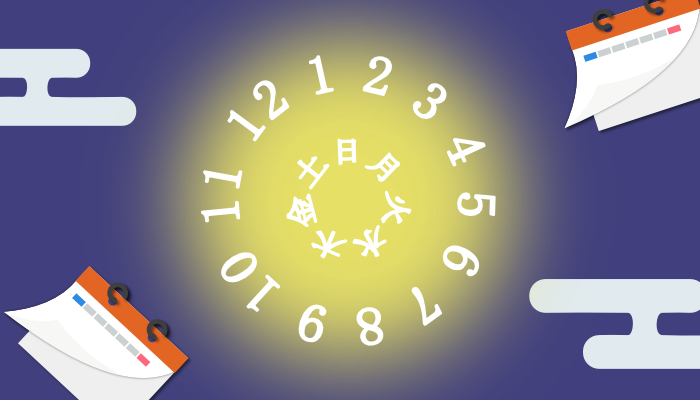鎌倉時代
鎌倉時代*かまくらじだいの元号*年号は、「文治」から「正慶」まで「49」の元号が存在している。
文治 ぶんじ
元暦2年8月14日
1185年9月9日
文治6年4月11日
1190年5月16日
6年
第82代 後鳥羽天皇 ごとばてんのう
在位
寿永2年8月20日-建久9年1月11日
1183年9月8日-1198年2月18日
火災
文治地震
「礼記」祭法
礼記*らいきとは、古代中国の経書。
湯以寛治民、而除其虐、文王以文治
建久 けんきゅう
文治6年4月11日
1190年5月16日
建久10年4月27日
1199年5月23日
10年
第82代 後鳥羽天皇 ごとばてんのう
在位
寿永2年8月20日-建久9年1月11日
1183年9月8日-1198年2月18日
第83代 土御門天皇 つちみかどてんのう
在位
建久9年1月11日-承元4年11月25日
1198年2月18日-1210年12月12日
三合の厄*さんごうのやく
/ 暦の上で一年に大歳・太陰・客気の三神が合することで大凶とし、この年は天災、兵乱などが多いとすることから「三合の厄」を避けるため
地震
「三国志」呉志 巻7
三国志*さんごくしとは、古代中国の春秋時代*しゅんじゅうじだいのことを記した歴史書。
安国和民建久長之計
「晋書」巻46 劉頌伝
晋書*しんじょとは、古代中国王朝「晋*しん」のことを記した歴史書。
建久安於万歳、垂長世於無窮
正治 しょうじ
建久10年4月27日
1199年5月23日
正治3年2月13日
1201年3月19日
3年
第83代 土御門天皇 つちみかどてんのう
在位
建久9年1月11日-承元4年11月25日
1198年2月18日-1210年12月12日
後鳥羽天皇からの譲位*じょうい
/ 天皇や君主が存命中にその地位を後継者に譲ることを受けて、第一皇子である為仁親王*ためひとしんのうがわずか3歳で践祚*せんそ
/ 天皇の位を受け継ぐことし、土御門天皇となったことによる改元
「荘子」雑篇 漁父
中国戦国時代の思想家 荘子*そうしの思想を記した思想書
天子、諸侯、大夫、庶人、此四者、自正、治之美也
建仁 けんにん
正治3年2月13日
1201年3月19日
建仁4年2月20日
1204年3月23日
4年
83代 土御門天皇 つちみかどてんのう
在位
建久9年1月11日-承元4年11月25日
1198年2月18日-1210年12月12日
辛酉革命*しんゆうかくめい
/ 60年に一度くる「辛酉」の年に起こるとされる革命を避けるため
「文選」巻47 聖主得賢臣頌
文選*もんぜんとは、古代中国の詩文集。
夫竭智附賢者、必建仁策、索人求士者、必樹伯跡
元久 げんきゅう
建仁4年2月20日
1204年3月23日
元久3年4月27日
1206年6月5日
3年
第83代 土御門天皇 つちみかどてんのう
在位
建久9年1月11日-承元4年11月25日
1198年2月18日-1210年12月12日
甲子革令*かっしかくめい
/ 60年に一度くる「甲子」の年に起こるとされる革命を避けるため
「毛詩正義」
毛詩正義*もうしせいぎとは、古代中国の思想家 孔子*こうしが編んだ*あんだ
/ 編集したとされる中国最古の詩集「毛詩*もうし」の注釈書。
文王建元久矣
建永 けんえい
元久3年4月27日
1206年6月5日
建永2年10月25日
1207年11月16日
2年
第83代 土御門天皇 つちみかどてんのう
在位
建久9年1月11日-承元4年11月25日
1198年2月18日-1210年12月12日
赤斑瘡*せきはんそう
/ 麻疹 はしかの流行
摂政 九条良経*くじょうよしつねの急死
「文選」巻42 曹子建與楊德祖書
吾雖德薄、位為蕃侯、猶庶幾戮力上國、流惠下民。建永世之業、留金石之功、豈徒以翰墨為勳績、辭賦為君子哉
承元 じょうげん
建永2年10月25日
1207年11月16日
承元5年3月9日
1211年4月23日
5年
第84代 順徳天皇 じゅんとくてんのう
在位
承元4年11月25日-承久3年4月20日
1210年12月12日-1221年5月13日
天然痘*てんねんとう
/ 疱瘡 ほうそうの流行
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
洪水
三合の厄*さんごうのやく
/ 暦の上で一年に大歳・太陰・客気の三神が合することで大凶とし、この年は天災、兵乱などが多いとすることから「三合の厄」を避けるため
「通典」巻55
通典*つてんとは、古代中国王朝「唐*とう」の歴史家 杜佑*とゆうが書いた、唐代に至るまでの古代中国の政治や法令制度の沿革とその変遷*へんせん
/ 時の流れとともに物事が移り変わることを綴った政書。
古者祭以酉時、薦以仲月、近代相承、元日奏祥瑞
建暦 けんりゃく
承元5年3月9日
1211年4月23日
建暦3年12月6日
1214年1月18日
3年
第84代 順徳天皇 じゅんとくてんのう
在位
承元4年11月25日-承久3年4月20日
1210年12月12日-1221年5月13日
土御門天皇からの譲位*じょういを受けて、異母弟である守成親王*もりなりしんのうが14歳で践祚*せんそし、順徳天皇となったことによる改元
「後漢書」巻12 律暦志
後漢書*ごかんじょとは、古代中国王朝「後漢*ごかん」のことを記した歴史書。
建暦之本必先立元、元正然後定日比定
「宋書」巻12
宋書*そうじょとは、古代中国の南北朝時代の南朝の国 宋*そうのことを記した歴史書。
建暦之本、必先立元
建保 けんぽう
建保 けんほう
建暦3年12月6日
1214年1月18日
建保7年4月12日
1219年5月27日
7年
第84代 順徳天皇 じゅんとくてんのう
在位
承元4年11月25日-承久3年4月20日
1210年12月12日-1221年5月13日
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
地震
「書経(尚書)」周書 多士
書経*しょきょうとは、古代中国の経書。
惟天丕建、保乂有殷
承久 じょうきゅう
承久 しょうきゅう
建保7年4月12日
1219年5月27日
承久4年4月13日
1222年5月25日
4年
第84代 順徳天皇 じゅんとくてんのう
在位
承元4年11月25日-承久3年4月20日
1210年12月12日-1221年5月13日
第85代 仲恭天皇 ちゅうきょうてんのう
在位
承久3年4月20日-承久7月9日
1221年5月13日-1221年7月29日
第86代 後堀河天皇 ごほりかわてんのう
在位
承久3年7月9日-貞永元年10月4日
1221年7月29日-1232年11月17日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
干魃*かんばつ
/ 農作物に必要な雨が長い間降らず作物が不作
三合の厄*さんごうのやく
/ 暦の上で一年に大歳・太陰・客気の三神が合することで大凶とし、この年は天災、兵乱などが多いとすることから「三合の厄」を避けるため
「詩緯」
詩緯*しいとは、古代中国の思想家 孔子*こうしが編んだ*あんだ
/ 編集したとされる中国最古の詩集「詩経*しきょう」ついて書かれた注釈書。
周起自后稷、歴世相承久
貞応 じょうおう
承久4年4月13日
1222年5月25日
貞応3年11月20日
1224年12月31日
3年
第86代 後堀河天皇 ごほりかわてんのう
在位
承久3年7月9日-貞永元年10月4日
1221年7月29日-1232年11月17日
幕府の手によって仲恭天皇が廃位させられてことに伴って、守貞親王の第三皇子である茂仁親王*とよひとしんのうが践祚*せんそし、後堀河天皇となったことによる改元
「易経(周易)」彖下
中孚以利貞、乃応乎天也
元仁 げんにん
貞応3年11月20日
1224年12月31日
元仁2年4月20日
1225年5月28日
2年
第86代 後堀河天皇 ごほりかわてんのう
在位
承久3年7月9日-貞永元年10月4日
1221年7月29日-1232年11月17日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
炎旱*えんかん
/ 日照り続きで作物が不作
「易経(周易)」乾卦
元亨利貞、正義曰、元則仁也
嘉禄 かろく
元仁2年4月20日
1225年5月28日
嘉禄3年12月10日
1228年1月18日
3年
第86代 後堀河天皇 ごほりかわてんのう
在位
承久3年7月9日-貞永元年10月4日
1221年7月29日-1232年11月17日
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
天然痘*てんねんとう
/ 疱瘡 ほうそうの流行
「博物志」
博物志*はくぶつしとは、古代中国王朝「晋*しん」に著した、中国および諸外国の事物を雑記した書物。
陛下摛顕先帝光耀、以奉皇天嘉禄
安貞 あんてい
嘉禄3年12月10日
1228年1月18日
安貞3年3月5日
1229年3月31日
3年
第86代 後堀河天皇 ごほりかわてんのう
在位
承久3年7月9日-貞永元年10月4日
1221年7月29日-1232年11月17日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
天然痘*てんねんとう
/ 疱瘡 ほうそうの流行
三合の厄*さんごうのやく
/ 暦の上で一年に大歳・太陰・客気の三神が合することで大凶とし、この年は天災、兵乱などが多いとすることから「三合の厄」を避けるため
「易経(周易)」上経坤
乃終有慶、安貞之吉、応地无疆
寛喜 かんぎ
寛喜 かんき
安貞3年3月5日
1229年3月31日
寛喜4年4月2日
1232年4月23日
4年
第86代 後堀河天皇 ごほりかわてんのう
在位
承久3年7月9日-貞永元年10月4日
1221年7月29日-1232年11月17日
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
飢饉*ききん
/ 作物の不作により人々がうえ苦しむこと
「魏書」
魏書*ぎしょとは、古代中国の南北朝時代の国「北周*ほくしゅう」のことを記した歴史書。
仁興温良、寛興喜楽
貞永 じょうえい
寛喜4年4月2日
1232年4月23日
貞永2年4月15日
1233年5月25日
2年
第86代 後堀河天皇 ごほりかわてんのう
在位
承久3年7月9日-貞永元年10月4日
1221年7月29日-1232年11月17日
第87代 四条天皇 しじょうてんのう
在位
貞永元年10月4日-仁治3年1月9日
1232年11月17日-1242年2月10日
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
飢饉*ききん
/ 作物の不作により人々がうえ苦しむこと
「易経(周易)」坤卦 注疏
利在永貞、永長也、貞正也、言能貞正也
天福 てんぷく
天福 てんふく
貞永2年4月15日
1233年5月25日
天福2年11月5日
1234年11月27日
2年
第87代 四条天皇 しじょうてんのう
在位
貞永元年10月4日-仁治3年1月9日
1232年11月17日-1242年2月10日
後堀河天皇からの譲位*じょういを受けて、第一皇子である秀仁親王*みつひとしんのうがわずか2歳で践祚*せんそし、順徳天皇となったことによる改元
「書経(尚書)」湯誥
政善、天福之
文暦 ぶんりゃく
天福2年11月5日
1234年11月27日
文暦2年9月19日
1235年11月1日
2年
87代 四条天皇 しじょうてんのう
在位
貞永元年10月4日-仁治3年1月9日
1232年11月17日-1242年2月10日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
地震
「文選」巻46 顔延三月三日曲水詩序
皇上以叡文承暦、景屬宸居
「旧唐書」
旧唐書*くとうじょとは、古代中国王朝「唐*とう」の史実を記した歴史書。
掌天文暦数
嘉禎 かてい
文暦2年9月19日
1235年11月1日
嘉禎4年11月23日
1238年12月30日
4年
第87代 四条天皇 しじょうてんのう
在位
貞永元年10月4日-仁治3年1月9日
1232年11月17日-1242年2月10日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
地震頻発
「北斉書」巻4 文宣紀
北斉書*ほくせいしょとは、古代中国の南北朝時代の北朝の国「東魏*とうぎ」と「北斉*ほくせい」のことを記した歴史書。
蘊千祀、彰明嘉禎
暦仁 りゃくにん
嘉禎4年11月23日
1238年12月30日
暦仁2年2月7日
1239年3月13日
2年
第87代 四条天皇 しじょうてんのう
在位
貞永元年10月4日-仁治3年1月9日
1232年11月17日-1242年2月10日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
「隋書」巻15 音楽志下
隋書*ずいしょとは、古代中国王朝「隋*ずい」のことを記した歴史書。
皇明馭暦、仁深海県
延応 えんおう
暦仁2年2月7日
1239年3月13日
延応2年7月16日
1240年8月5日
2年
第87代 四条天皇 しじょうてんのう
在位
貞永元年10月4日-仁治3年1月9日
1232年11月17日-1242年2月10日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
地震
「文選」巻24 潘安仁為賈謐作贈陸機
廊廟惟清、俊乂是延、擢応嘉挙
仁治 にんじ
仁治 にんち
延応2年7月16日
1240年8月5日
仁治4年2月26日
1243年3月18日
4年
第87代 四条天皇 しじょうてんのう
在位
貞永元年10月4日-仁治3年1月9日
1232年11月17日-1242年2月10日
第88代 後嵯峨天皇 ごさがてんのう
在位
仁治3年1月20日-寛元4年1月29日
1242年2月21日-1246年2月16日
彗星出現*すいせいしゅつげん
/ 大な災害が起こる前触れとして不吉とされていた
干魃*かんばつ
/ 農作物に必要な雨が長い間降らず作物が不作
炎旱*えんかん
/ 日照り続きで作物が不作
地震など
「新唐書」
新唐書*しんとうじょとは、古代中国王朝「唐*とう」の史実を記した歴史書「旧唐書*くとうじょ」に改修を加えた歴史書。
太宗以寛仁治天下
寛元 かんげん
仁治4年2月26日
1243年3月18日
寛元5年2月28日
1247年4月5日
5年
第88代 後嵯峨天皇 ごさがてんのう
在位
仁治3年1月20日-寛元4年1月29日
1242年2月21日-1246年2月16日
第89代 後深草天皇 ごふかくさてんのう
在位
寛元4年1月29日-正元元年11月26日
1246年2月16日-1260年1月9日
四条天皇の崩御*ほうぎょに伴い、土御門天皇の皇子である邦仁親王*くにひとしんのうがわずか2歳で践祚*せんそし、後嵯峨天皇となったことによる改元
「宋書」
舜禹之際、五教在寛、元元以平
宝治 ほうじ
寛元5年2月28日
1247年4月5日
宝治3年3月18日
1249年5月2日
3年
第89代 後深草天皇 ごふかくさてんのう
在位
寛元4年1月29日-正元元年11月26日
1246年2月16日-1260年1月9日
後嵯峨天皇からの譲位*じょういを受けて、久仁親王*ひさひとしんのうがわずか2歳で践祚*せんそし、後深草天皇となったことによる改元
「春秋繁露」通国身
春秋繁露*しゅんじゅうはんろとは、古代中国王朝「前漢*ぜんかん」の論文集。
気之清者為精、人之清者為賢、治身者以積精為宝、治国者以積賢為道
建長 けんちょう
宝治3年3月18日
1249年5月2日
建長8年10月5日
1256年10月24日
8年
第89代 後深草天皇 ごふかくさてんのう
在位
寛元4年1月29日-正元元年11月26日
1246年2月16日-1260年1月9日
天変*
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
平安京の内裏火災*だいりかさい
/ 天皇が住んでいるところの火災
「後漢書」巻65 段熲伝
建長久之策
康元 こうげん
建長8年10月5日
1256年10月24日
康元2年3月14日
1257年3月31日
2年
第89代 後深草天皇 ごふかくさてんのう
在位
寛元4年1月29日-正元元年11月26日
1246年2月16日-1260年1月9日
赤斑瘡*せきはんそう
/ 麻疹 はしかの流行
-
正嘉 しょうか
康元2年3月14日
1257年3月31日
正嘉3年3月26日
1259年4月20日
3年
第89代 後深草天皇 ごふかくさてんのう
在位
寛元4年1月29日-正元元年11月26日
1246年2月16日-1260年1月9日
太政官庁*だいじょうかん、五条殿*ごじょうどのなどの焼失
「芸文類聚」歳時中 元正
芸文類聚*げいもんるいじゅうとは、古代中国の百科事典。
採秦漢之旧儀、肇元正之嘉会
正元 しょうげん
正嘉3年3月26日
1259年4月20日
正元2年4月13日
1260年5月24日
2年
第89代 後深草天皇 ごふかくさてんのう
在位
寛元4年1月29日-正元元年11月26日
1246年2月16日-1260年1月9日
第90代 亀山天皇 かめやまてんのう
在位
正元元年11月26日-文永11年1月26日
1260年1月9日-1274年3月6日
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
飢饉*ききん
/ 作物の不作により人々がうえ苦しむこと
「詩緯」
一如正元、万載相伝
文応 ぶんおう
正元2年4月13日
1260年5月24日
文応2年2月20日
1261年3月22日
2年
第90代 亀山天皇 かめやまてんのう
在位
正元元年11月26日-文永11年1月26日
1260年1月9日-1274年3月6日
後深草天皇からの譲位*じょういを受けて、弟である恒仁親王*つねひとしんのうが践祚*せんそし、亀山天皇となったことによる改元
「晋書」巻45 劉毅伝
大晋之行、戢武興文之応也
弘長 こうちょう
文応2年2月20日
1261年3月22日
弘長4年2月28日
1264年3月27日
4年
第90代 亀山天皇 かめやまてんのう
在位
正元元年11月26日-文永11年1月26日
1260年1月9日-1274年3月6日
辛酉革命*しんゆうかくめい
/ 60年に一度くる「辛酉」の年に起こるとされる革命を避けるため
「貞観政要」巻3 封建
貞観政要*じょうがんせいようとは、古代中国王朝 唐朝の第2代皇帝の太宗*たいそうの言行集。
閼治定之規、以弘長世之業者、万古不易、百慮同帰
文永 ぶんえい
弘長4年2月28日
1264年3月27日
文永12年4月25日
1275年5月22日
12年
第90代 亀山天皇 かめやまてんのう
在位
正元元年11月26日-文永11年1月26日
1260年1月9日-1274年3月6日
第91代 後宇陀天皇 ごうだてんのう
在位
文永11年1月26日-弘安10年10月21日
1274年3月6日-1287年11月27日
甲子革令*かっしかくめい
/ 60年に一度くる「甲子」の年に起こるとされる革命を避けるため
「後漢書」荀悦伝
漢四百有六載、揆乱反正、統武興文、永惟祖宗之洪業、思光啓万嗣
建治 けんじ
文永12年4月25日
1275年5月22日
建治4年2月29日
1278年3月23日
4年
第91代 後宇陀天皇 ごうだてんのう
在位
文永11年1月26日-弘安10年10月21日
1274年3月6日-1287年11月27日
亀山天皇からの譲位*じょういを受けて、第二皇子である世仁親王*よひとしんのうが践祚*せんそし、後宇多天皇となったことによる改元
「周礼」
周礼*しゅらいとは、古代中国の経書。
以治建国之学
弘安 こうあん
建治4年2月29日
1278年3月23日
弘安11年4月28日
1288年5月29日
11年
第91代 後宇陀天皇 ごうだてんのう
在位
文永11年1月26日-弘安10年10月21日
1274年3月6日-1287年11月27日
第92代 伏見天皇 ふしみてんのう
在位
弘安10年10月21日-永仁6年7月22日
1287年11月27日-1298年8月30日
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
「唐太宗実録」
唐太宗実録実録*とうたいそうじつろくとは、古代中国王朝「唐*とう」の皇帝の言行を記した記録。
弘安民之道
正応 しょうおう
弘安11年4月28日
1288年5月29日
正応6年8月5日
1293年9月6日
6年
第92代 伏見天皇 ふしみてんのう
在位
弘安10年10月21日-永仁6年7月22日
1287年11月27日-1298年8月30日
後宇多天皇からの譲位*じょういを受けて、従兄である熈仁親王*ひろひとしんのうが践祚*せんそし、伏見天皇となったことによる改元
「毛詩」
毛詩*もうしとは、古代中国の思想家 孔子*こうしが編んだ*あんだ
/ 編集したとされる中国最古の詩集。
徳正応利
永仁 えいにん
正応6年8月5日
1293年9月6日
永仁7年4月25日
1299年5月25日
7年
第92代 伏見天皇 ふしみてんのう
在位
弘安10年10月21日-永仁6年7月22日
1287年11月27日-1298年8月30日
第93代 後伏見天皇 ごふしみてんのう
在位
永仁6年7月22日-正安3年1月21日
1298年8月30日-1301年3月2日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
鎌倉大地震
「晋書」巻22 楽志
永載仁風、長撫無外
正安 しょうあん
永仁7年4月25日
1299年5月25日
正安4年11月21日
1302年12月10日
4年
第93代 後伏見天皇 ごふしみてんのう
在位
永仁6年7月22日-正安3年1月21日
1298年8月30日-1301年3月2日
第94代 後二条天皇 ごにじょうてんのう
在位
正安3年1月21日-徳治3年8月25日
1301年3月2日-1308年9月10日
伏見天皇からの譲位*じょういを受けて、第一皇子である胤仁親王*たねひとしんのうが11歳で践祚*せんそし、後伏見天皇となったことによる改元
「周書」
周書*しゅうしょとは、古代中国の南北朝時代の国「北周*ほくしゅう」のことを記した歴史書。
居正安其身
「孔子家語」
孔子家語*こうしけごとは、古代中国の思想家 孔子*こうしの言行、逸話を集録した書物。
此の五行は 是れ以て身を正し 國を安んずるに足る
乾元 けんげん
正安4年11月21日
1302年12月10日
乾元2年8月5日
1303年9月16日
2年
第94代 後二条天皇 ごにじょうてんのう
在位
正安3年1月21日-徳治3年8月25日
1301年3月2日-1308年9月10日
後伏見天皇からの譲位*じょういを受けて、第一皇子である邦治親王*くにはるしんのうが11歳で践祚*せんそし、後二条天皇となったことによる改元
「周易(易経)」
周易*しゅうえきとは、古代中国の儒教の経典「易経*えききょう」の古名。
大哉乾元、万物資始、乃統天
嘉元 かげん
乾元2年8月5日
1303年9月16日
嘉元4年12月14日
1307年1月18日
4年
第94代 後二条天皇 ごにじょうてんのう
在位
正安3年1月21日-徳治3年8月25日
1301年3月2日-1308年9月10日
彗星出現*すいせいしゅつげん
/ 大な災害が起こる前触れとして不吉とされていた
炎旱*えんかん
/ 日照り続きで作物が不作
「芸文類聚」巻1 天部 賀老人星表
嘉占元吉、弘無量之祐、隆克昌之祚、普天同慶、率土合歓
「貞観政要」
元良盛なるを嘉して万国貞し
徳治 とくじ
嘉元4年12月14日
1307年1月18日
徳治3年10月9日
1308年11月22日
3年
第95代 花園天皇 はなぞのてんのう
在位
延慶元年8月26日-文保2年2月26日
1308年9月11日-1318年3月29日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
「書経(尚書)」皋陶謨 注疏
俊徳治能之士並在官
「春秋左氏伝」巻7 僖公33年
春秋左氏伝*しゅんじゅうさしでんとは、古代中国の春秋時代*しゅんじゅうじだいのことを記した歴史書「春秋」の注釈書。
能敬必有徳、徳以治民
「魏書」
明王以徳治天下
延慶 えんきょう
延慶 えんけい
徳治3年10月9日
1308年11月22日
延慶4年4月28日
1311年5月17日
4年
第95代 花園天皇 はなぞのてんのう
在位
延慶元年8月26日-文保2年2月26日
1308年9月11日-1318年3月29日
後二条天皇の突然の崩御*ほうぎょに伴い、伏見天皇の第四皇子である富仁親王*とみひとしんのうが12歳で践祚*せんそし、花園天皇となったことによる改元
「後漢書」巻52 馬武伝
以功名延慶于後
応長 おうちょう
延慶4年4月28日
1311年5月17日
応長2年3月20日
1312年4月27日
2年
第95代 花園天皇 はなぞのてんのう
在位
延慶元年8月26日-文保2年2月26日
1308年9月11日-1318年3月29日
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
「旧唐書」巻22 礼儀志
応長暦之規、象中月之度、広綜陰陽之数、傍通寒暑之和
正和 しょうわ
応長2年3月20日
1312年4月27日
正和6年2月3日
1317年3月16日
6年
第95代 花園天皇 はなぞのてんのう
在位
延慶元年8月26日-文保2年2月26日
1308年9月11日-1318年3月29日
日食*にっしょく
/ 月が太陽の前を横切ることで、太陽の一部または全部が隠される現象
月食*げっしょく
/ 太陽、地球、月が一直線に並び、月が地球の影に入ることで、月が暗く見えたり、欠けて見える現象
地震
怪異*かいい
/ 現実にはあり得ないと思われるような不思議な事柄
「資治通鑑」唐紀
資治通鑑*しじつがんとは、古代中国王朝「北宋*ほくそう」の儒学者 司馬光*しばこうの著した歴史書。
皇帝受朝奏正和
文保 ぶんぽう
文保 ぶんほう
正和6年2月3日
1317年3月16日
文保3年4月28日
1319年5月18日
3年
第95代 花園天皇 はなぞのてんのう
在位
延慶元年8月26日-文保2年2月26日
1308年9月11日-1318年3月29日
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
大地震
「梁書」
梁書*りょうしょとは、古代中国の南北朝時代の国「梁*りょう」のことを記した歴史書。
姫周基文、久保七百
元応 げんおう
文保3年4月28日
1319年5月18日
元応3年2月23日
1321年3月22日
3年
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
花園天皇からの譲位*じょういを受けて、後宇多天皇の第二皇子である尊治親王*たかはるしんのうが11歳で践祚*せんそし、後醍醐天皇となったことによる改元
「旧唐書」
陛下富教安人、務農敦本、光復社稷、康済黎元之応也
元亨 げんこう
元応3年2月23日
1321年3月22日
元亨4年12月9日
1324年12月25日
4年
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
辛酉革命*しんゆうかくめい
/ 60年に一度くる「辛酉」の年に起こるとされる革命を避けるため
「周易(易経)」彖上
其徳剛健而文明、応乎天、而時行、是以元亨
正中 しょうちゅう
元亨4年12月9日
1324年12月25日
正中3年4月26日
1326年5月28日
3年
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
甲子革令*かっしかくめい
/ 60年に一度くる「甲子」の年に起こるとされる革命を避けるため
「易経(周易)」文言伝
見龍在田利見大人、何謂也、子曰、龍徳而正中者也、又曰、需有孚、元亨、貞吉位乎天位、以正中也
嘉暦 かりゃく
正中3年4月26日
1326年5月28日
嘉暦4年8月29日
1329年9月22日
4年
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
洪水
地震
「旧唐書」巻13 本紀
四序嘉辰、暦代増置、宋韻曰、暦数也
元徳 げんとく
嘉暦4年8月29日
1329年9月22日
大覚寺統
元徳3年8月9日
1331年9月11日
持明院統
元徳4年4月28日
1332年5月23日
大覚寺統
3年
持明院統
4年
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
「易経(周易)」
乾元亨利貞
「周易正義」
周易正義*しゅうえきせいぎとは、古代中国の儒教の経典「周易*しゅうえき
/ 易経」の注釈書。
元者善之長、謂天之元徳、始生万物
大覚寺統
大覚寺統*だいかくじとうとは、鎌倉後期から南北朝時代にかけて皇位継承*こういけいしょう
/ 天皇の位を受け継ぐことをめぐって争った2つの皇統のうち、亀山天皇の系統のこと。
後宇多天皇の院御所だった京都嵯峨にある寺院「大覚寺」が名の由来となっている。
元弘 げんこう
元徳3年8月9日
1331年9月11日
元弘4年1月29日
1334年3月5日
4年
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
「芸文類聚」巻1 天部
老人星体色光明、嘉占元吉、弘無量之裕降克昌之祥、普天同慶率土合歓
持明院統
持明院統*じみょういんとうとは、鎌倉後期から南北朝時代にかけて皇位継承*こういけいしょう / 天皇の位を受け継ぐことをめぐって争った2つの皇統のうち、後深草天皇の系統のこと。
後深草天皇の院御所だった京都にある寺院「持明院」が名の由来となっている。
正慶 しょうけい
正慶 しょうきょう
元徳4年4月28日
1332年5月23日
正慶2年5月25日
1333年7月7日
2年
北朝第1代 光厳天皇 こうごんてんのう
在位
元弘元年9月20日-正慶2年5月25日
1331年10月22日-1333年7月7日
後伏見天皇からの譲位*じょういを受けて、第一皇子である邦治親王*くにはるしんのうが19歳で践祚*せんそし、後二条天皇となったことによる改元
「易経(周易)」益卦 注
以中正有慶之徳、有攸往也、何適而不利哉