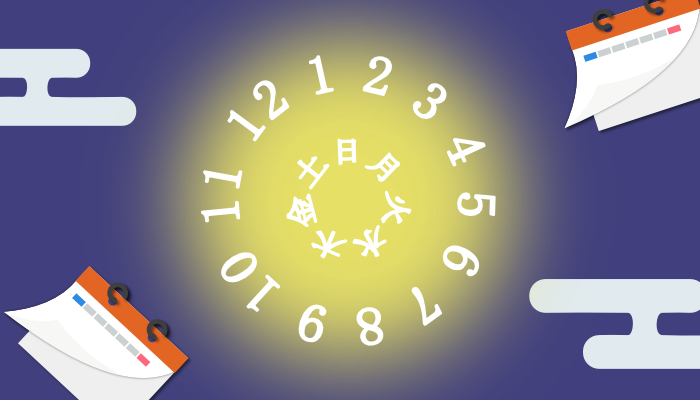南北朝時代
南北朝時代*なんぼくちょうじだいの元号*年号は、「南朝」が「9」の元号、「北朝」が「17」の元号が存在している。
南朝
南朝*なんちょうとは、室町幕府 初代征夷大将軍 足利尊氏*あしかが たかうじによって謀反を起こされた大覚寺統*だいかくじとうの後醍醐天皇が、京都から大和国*やまとのくに
/ 奈良県南部に位置する吉野へと逃れ、北朝と室町幕府に対立する形で吉野に拠点を設けた朝廷のこと。
建武 けんむ
元弘4年1月29日
1334年3月5日
南朝
建武3年2月29日
1336年4月11日
北朝
建武5年8月28日
1338年10月11日
南朝
3年
北朝
5年
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
擾乱帰正*
/ ある混乱や騒動、不正などから本来の状態や秩序に戻ること
「文選」宣徳皇后令 任彦升
文選*もんぜんとは、古代中国の詩文集。
隆昌季年勤王始著、建武惟新、締構斯在
延元 えんげん
建武3年2月29日
1336年4月11日
延元5年4月28日
1340年5月25日
5年
第96代 後醍醐天皇 ごだいごてんのう
在位
文保2年2月26日-延元4年8月15日
1318年3月29日-1339年9月18日
第97代 後村上天皇 ごむらかみてんのう
在位
延元4年8月15日-正平23年3月11日
1339年9月18日-1368年3月29日
戦乱*せんらん
/ 建武の乱
「梁書」
梁書*りょうしょとは、古代中国の南北朝時代の国「梁*りょう」のことを記した歴史書。
沈休文等奏言、聖徳所被、上自蒼蒼、下延元元
興国 こうこく
延元5年4月28日
1340年5月25日
興国7年12月8日
1347年1月20日
7年
第97代 後村上天皇 ごむらかみてんのう
在位
延元4年8月15日-正平23年3月11日
1339年9月18日-1368年3月29日
後醍醐天皇からの譲位*じょうい
/ 天皇や君主が存命中にその地位を後継者に譲ることを受けて、第7皇子である義良親王*のりよししんのうが践祚*せんそ
/ 天皇の位を受け継ぐことし、後村上天皇となったことによる改元
-
正平 しょうへい
興国7年12月8日
1347年1月20日
正平25年7月24日
1370年8月16日
25年
第97代 後村上天皇 ごむらかみてんのう
在位
延元4年8月15日-正平23年3月11日
1339年9月18日-1368年3月29日
第98代 長慶天皇 ちょうけいてんのう
在位
正平23年3月-弘和3年冬
1368年3月-1383年冬
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
戦乱
-
建徳 けんとく
正平25年7月24日
1370年8月16日
建徳3年4月
1372年5月
3年
第98代 長慶天皇 ちょうけいてんのう
在位
正平23年3月-弘和3年冬
1368年3月-1383年冬
後村上天皇の崩御*ほうぎょに伴い、第一皇子である寛成親王*ゆたなりしんのうが践祚*せんそし、長慶天皇となったことによる改元
「文選」巻2
建至徳以創洪業
文中 ぶんちゅう
建徳3年4月
1372年5月
文中4年5月27日
1375年6月26日
4年
第98代 長慶天皇 ちょうけいてんのう
在位
正平23年3月-弘和3年冬
1368年3月-1383年冬
天災地変*てんさいちへん
/ 自然界の変動によって起こる災害や異変
-
天授 てんじゅ
文中4年5月27日
1375年6月26日
天授7年2月10日
1381年3月6日
7年
第98代 長慶天皇 ちょうけいてんのう
在位
正平23年3月-弘和3年冬
1368年3月-1383年冬
山崩れ
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
「史記」巻92 淮陰侯列伝
史記*しきとは、中国最初の歴史書。
且陛下所謂天授、非人力也
また陛下の能力はいわゆる天から授けられた能力であって、人の力ではない
弘和 こうわ
天授7年2月10日
1381年3月6日
弘和4年4月28日
1384年5月18日
4年
第98代 長慶天皇 ちょうけいてんのう
在位
正平23年3月-弘和3年冬
1368年3月-1383年冬
第99代 後亀山天皇 ごかめやまてんのう
在位
弘和3年冬-元中9年閏10月5日
1383年冬-1392年11月19日
辛酉革命*しんゆうかくめい
/ 60年に一度くる「辛酉」の年に起こるとされる革命を避けるため
-
元中 げんちゅう
弘和4年4月28日
1384年5月18日
元中9年閏10月5日
1392年11月19日
9年
第99代 後亀山天皇 ごかめやまてんのう
在位
弘和3年冬-元中9年閏10月5日
1383年冬-1392年11月19日
慶天皇からの譲位*じょういを受けて、弟である熙成親王*ひろなりしんのうが践祚*せんそし、後亀山天皇となったことによる改元
甲子革令*かっしかくめい
/ 60年に一度くる「甲子」の年に起こるとされる革命を避けるため
-
北朝
北朝*ほくちょうとは、後醍醐天皇*ごだいごてんのうにより天皇を中心とした政治が行われた「建武の新政」が約3年ほどで崩壊したことを受けて、室町幕府 初代征夷大将軍 足利尊氏*あしかが たかうじが持明院統*じみょういんとうの光明天皇*こうみょうてんのうを擁立*ようりつ
/ 支持して首位に就かせることし、京都に拠点を設けた朝廷のこと。
暦応 りゃくおう
暦応 れきおう
建武5年8月28日
1338年10月11日
暦応5年4月27日
1342年6月1日
5年
第1代 光厳天皇 こうごんてんのう
在位
元弘元年9月20日-正慶2年5月25日
1331年10月22日-1333年7月7日
第2代 光明天皇 こうみょうてんのう
在位
lb-貞和4年10月27日
1336年9月20日-1348年11月18日
後醍醐天皇に廃位*はいい
/ 在位している君主を強要して退かせることされていた光厳上皇からの院宣*いんぜん
/ 上皇や法皇の命令を受けて出す文書を受けて、弟である豊仁親王*ゆたひとしんのうが践祚し、光明天皇となったことによる改元
「帝王代記」
帝王代記*ていおうだいきとは、歴代天皇の事跡を年代順に記録した年代記。
堯時有草、夾階而生、王者以是占暦、応和而生
康永 こうえい
暦応5年4月27日
1342年6月1日
康永4年10月21日
1345年11月15日
4年
第2代 光明天皇 こうみょうてんのう
在位
建武3年8月15日-貞和4年10月27日
1336年9月20日-1348年11月18日
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
「漢書」
漢書*かんじょとは、古代中国王朝 前漢*ぜんかんのことを記した歴史書。
海内康平、永保国家
貞和 じょうわ
貞和 ていわ
康永4年10月21日
1345年11月15日
貞和6年2月27日
1350年4月4日
6年
第2代 光明天皇 こうみょうてんのう
在位
建武3年8月15日-貞和4年10月27日
1336年9月20日-1348年11月18日
第3代 崇光天皇 すこうてんのう
在位
貞和4年10月27日-観応2年11月7日
1348年11月18日-1351年11月26日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
水害
「芸文類聚」帝王部
芸文類聚*げいもんるいじゅうとは、古代中国の百科事典。
体乾霊之休徳、稟貞和之純精
観応 かんのう
観応 かんおう
貞和6年2月27日
1350年4月4日
観応3年9月27日
1352年11月4日
3年
第3代 崇光天皇 すこうてんのう
在位
貞和4年10月27日-観応2年11月7日
1348年11月18日-1351年11月26日
第4代 後光厳天皇 ごこうごんてんのう
在位
観応3年8月17日-応安4年3月23日
1352年9月25日-1371年4月9日
後伏見天皇からの譲位*じょういを受けて、第一皇子である弥仁親王*いやひとしんのうが践祚*せんそし、崇光天皇となったことによる改元
「荘子」外篇天地
荘子*そうしとは、中国戦国時代の思想家 荘子*の思想を記した思想書。
玄古之君天下無為也、疏曰、以虚通之理、観応物之数而無為
文和 ぶんな
文和 ぶんわ
観応3年9月27日
1352年11月4日
文和5年3月28日
1356年4月29日
5年
第4代 後光厳天皇 ごこうごんてんのう
在位
観応3年8月17日-応安4年3月23日
1352年9月25日-1371年4月9日
崇光天皇が南朝によって退位させられたことに伴い、弟である弥仁親王*いやひとしんのうが践祚*せんそし、後光厳天皇となったことによる改元
「旧唐書」巻14 順宗紀
旧唐書*くとうじょとは、古代中国王朝「唐*とう」の史実を記した歴史書。
叡哲温文、寛和仁恵
「三国志」呉志 孫権伝
三国志*さんごくしとは、古代中国の春秋時代*しゅんじゅうじだいのことを記した歴史書。
文和於内、武信于外
延文 えんぶん
文和5年3月28日
1356年4月29日
延文6年3月29日
1361年5月4日
6年
第4代 後光厳天皇 ごこうごんてんのう
在位
観応3年8月17日-応安4年3月23日
1352年9月25日-1371年4月9日
戦乱
「漢書」巻88 儒林伝
延文学儒者以百数
康安 こうあん
延文6年3月29日
1361年5月4日
康安2年9月23日
1362年10月11日
2年
第4代 後光厳天皇 ごこうごんてんのう
在位
観応3年8月17日-応安4年3月23日
1352年9月25日-1371年4月9日
戦乱
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
「旧唐書」巻28
作治康凱安之舞
「史記正義」
史記正義*しきせいぎとは、中国最初の歴史書「史記*しき」について書かれた注釈書。
天下衆事咸得康安、以致天下太平
貞治 じょうじ
貞治 ていじ
康安2年9月23日
1362年10月11日
貞治7年2月18日
1368年3月7日
7年
第4代 後光厳天皇 ごこうごんてんのう
在位
観応3年8月17日-応安4年3月23日
1352年9月25日-1371年4月9日
戦乱
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
地震
「易経(周易)」象下
易経*えききょうとは、古代中国の儒教の経典。
利武人之貞、志治也
応安 おうあん
貞治7年2月18日
1368年3月7日
応安8年2月27日
1375年3月29日
8年
第4代 後光厳天皇 ごこうごんてんのう
在位
観応3年8月17日-応安4年3月23日
1352年9月25日-1371年4月9日
第5代 後円融天皇 ごえんゆうてんのう
在位
応安4年3月23日-永徳2年4月11日
1371年4月9日-1382年5月24日
天変地妖*てんぺんちよう
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる変動と地震・津波・噴火・洪水・異常気象など地上に起こる変異
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
「毛詩正義」大雅江漢
毛詩正義*もうしせいぎとは、古代中国の思想家 孔子*こうしが編んだ*あんだ
/ 編集したとされる中国最古の詩集「毛詩*もうし」の注釈書。
今四方既已平、服王国之内、幸応安定
永和 えいわ
応安8年2月27日
1375年3月29日
永和5年3月22日
1379年4月9日
5年
第5代 後円融天皇 ごえんゆうてんのう
在位
応安4年3月23日-永徳2年4月11日
1371年4月9日-1382年5月24日
後伏見天皇からの譲位*じょういを受けて、第二皇子である緒仁親王*おひとしんのうが践祚*せんそし、後円融天皇となったことによる改元
「書経(尚書)」舜典
書経*しょきょうとは、古代中国の経書。
詩言志、歌永言、声依永、律和歌、八音克諧、無相奪倫、神人以和
「芸文類聚」巻8
九功六義之興、依永和声之製、志由興作、情以詞宣
康暦 こうりゃく
永和5年3月22日
1379年4月9日
康暦3年2月24日
1381年3月20日
3年
第5代 後円融天皇 ごえんゆうてんのう
在位
応安4年3月23日-永徳2年4月11日
1371年4月9日-1382年5月24日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
疾疫*しつえき
/ 悪性の流行病
戦乱
「旧唐書」
承成康之暦業
永徳 えいとく
康暦3年2月24日
1381年3月20日
永徳4年2月27日
1384年3月19日
4年
第5代 後円融天皇 ごえんゆうてんのう
在位
応安4年3月23日-永徳2年4月11日
1371年4月9日-1382年5月24日
第6代 後小松天皇 ごこまつてんのう
在位
永徳2年4月11日-応永19年8月29日
1382年5月24日-1412年10月5日
辛酉革命*しんゆうかくめい
/ 60年に一度くる「辛酉」の年に起こるとされる革命を避けるため
-
至徳 しとく
永徳4年2月27日
1384年3月19日
至徳4年8月23日
1387年10月5日
4年
第6代 後小松天皇 ごこまつてんのう
在位
永徳2年4月11日-応永19年8月29日
1382年5月24日-1412年10月5日
後円融天皇からの譲位*じょういを受けて、第一皇子である幹仁親王*もとひとしんのうがわずか6歳で践祚*せんそし、後小松天皇となったことによる改元
甲子革令*かっしかくめい
/ 60年に一度くる「甲子」の年に起こるとされる革命を避けるため
「孝経」
孝経*こうきょうとは、古代中国の思想家 孔子*こうしの教えを弟子たちがまとめたとされる書物。
先王有至徳要道、以順天下
嘉慶 かけい
嘉慶 かきょう
至徳4年8月23日
1387年10月5日
嘉慶3年2月9日
1389年3月7日
3年
第6代 後小松天皇 ごこまつてんのう
在位
永徳2年4月11日-応永19年8月29日
1382年5月24日-1412年10月5日
疾疫(しつえき / 悪性の流行病)
「毛詩正義」
将有嘉慶、禎祥先来見也
康応 こうおう
嘉慶3年2月9日
1389年3月7日
康応2年3月26日
1390年4月12日
2年
第6代 後小松天皇 ごこまつてんのう
在位
永徳2年4月11日-応永19年8月29日
1382年5月24日-1412年10月5日
朝廷の重要な役職の人や、位の高い僧が相次いで亡くなったため
「文選」巻8 七啓
国富民康、神応烋臻、屡獲嘉祥
明徳 めいとく
康応2年3月26日
1390年4月12日
明徳5年7月5日
1394年8月2日
5年
第6代 後小松天皇 ごこまつてんのう
在位
永徳2年4月11日-応永19年8月29日
1382年5月24日-1412年10月5日
天変*てんぺん
/ 暴風雨・落雷・日食・月食・彗星など天空に起こる異変
戦乱
「礼記」大学
礼記*らいきとは、古代中国の経書。
大学之道、在明明徳、在親民