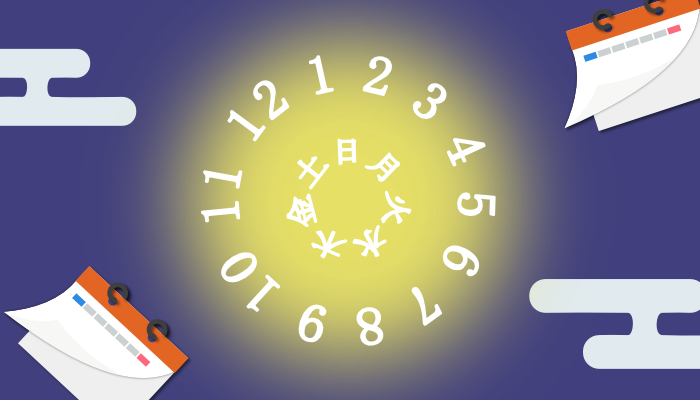雑節
雑節*ざっせつとは、中国から伝わった季節の移り変わりの目安とする「二十四節気*にじゅうしせっき」を補うかたちで、日本人の季節感や生活文化に合わせてつくられた日本独自のもの。
節分
節分*せつぶんとは、「季節を分ける」を意味し、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日のこと。
古くから季節の変わり目には邪気が生じると考えられており、さまざまな邪気祓いの行事が行われているが、現在では「春の節分」が重要視され、豆まきやその年の恵方を向いて恵方巻を食べる習慣などがある。
彼岸
彼岸*ひがんとは、春分または秋分を中日*ちゅうにちとして、前後各3日を合わせた各7日間のことで、彼岸の始めの日を「彼岸入り」彼岸の終わりを「彼岸の明け」という。
春分と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈み、昼と夜の長さが同じになることから、この世とあの世が通じやすくなると考えられ、先祖供養でお墓参りをする習慣が生まれたとされる。
社日
社日*しゃにちとは、春分または秋分に最も近い戊の日*つちのえのひのことで、春の社日は「春社*しゅんしゃ」、秋の社日は「秋社*しゅうしゃ」とも呼び、その土地の守護神「産土神*うぶすなかみ」を祀る日とされている。
春の社日は、種まきをする時期なので、五穀の種を供えて豊作を祈願し、秋の社日は、その年に収穫した初穂を供えて、その年の収穫に感謝する行事がそれぞれ行われている。
八十八夜
八十八夜*はちじゅうはちやとは、「立春」から数えて88日目にあたる日のことで、夏の気配が感じられるようになり、農家さんたちにとっては、種まきをする目安となる日のこと。
入梅
入梅*にゅうばいとは、梅雨に入る最初の日のことで、昔は二十四節気の「芒種*ぼうしゅ」を過ぎた後の最初の「壬の日*みずのえのひ」とされていたが、現在の気象学上では、太陽が黄経 80度を通過した日のこと。
半夏生
半夏生*はんげしょうとは夏至*げし」から数えて11日目のことだったが、現在では天球上の黄経 100度の点を太陽が通過する日のこと。
半夏生を過ぎて田植えをすると収穫が減ると言われ、田植えは半夏生に入る前に終わらせるものとされている。
土用
土用*どようとは、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の直前の18日間のことだが、現在は「夏の土用」が重要視されている。
中国伝来の陰陽五行説*いんようごぎょうせつでは、万物の根源とされる「木・火・土・金・水」を四季にあてはめると、「春=木」「夏=火」「秋=金」「冬=水」となり、あまった「土」を季節の変わり目の18~19日間を「土用」としていたのだとか。
昔は日にちを数えるときに、「子・丑・寅・卯」などと十二支で割り当てていたことから、土用の期間にめぐってくる丑の日のことを「土用の丑の日*どようのうしのひ」というのだそうだ。
また、その年によっては「土用の丑の日」が 2回めぐってくることもあり、その場合は1度目を「一の丑」、2度目を「二の丑」と呼び分けられている。
特に「夏の土用」は、一年のうちでもっとも暑さが厳しい期間にあたり体調を崩しやすくなるため、最も重要視されるようになり、この期間の「丑の日」に精のある鰻*うなぎを食べると夏バテしないと言われている。
二百十日
二百十日*にひゃくとおかとは、「立春」から数えて210日目のことで、農作物に甚大な影響を与える台風に見舞われることも多い時期であることから警戒すべきとする日。
二百ニ十日
二百ニ十日*にひゃくはつかとは、「立春」から数えて220日目のことで、「二百十日」同様に、農作物に甚大な影響を与える台風に見舞われることも多い時期であることから警戒すべきとする日。