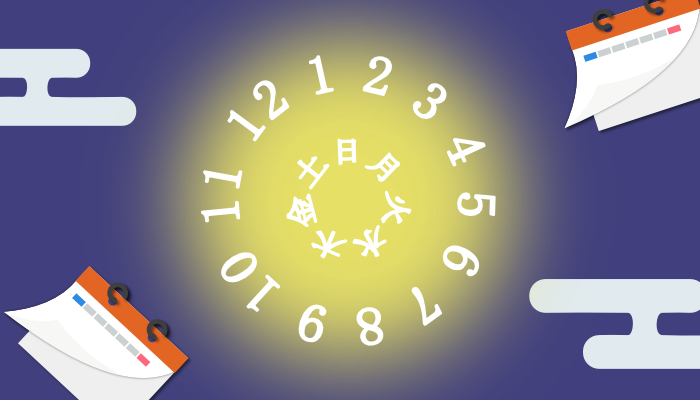二十四節気とは
陰暦で 1年を太陽の黄道上の位置に従って、春夏秋冬を 6つに分けることで 1年を 24等分し、季節を節目を表した約 15日ごとに移り変わる暦のこと。
中国の中華文化の発祥地である黄河中下流域にある平原「中原*ちゅうげん」の気候をもとに名付けられていることから、日本で体感する気候とは季節感が合わない名称や時期がある。
定期法
定気法*ていきほうとは、二十四節気を配置する方法のひとつで、太陽の天球上の通り道である黄道と、天の赤道の交点のひとつである「春分点」を基点として24等分し、15度ごとの黄経上の特定の度を太陽が通過する日に節気*正節と中気を交互に配していくこと。
平気法
平気法*へいきほう
/ 恒気法 こうきほうは、二十四節気を配置する方法のひとつで、冬至から翌年の冬至までの時間を24等分し、約15日ごとの分点に節気と中気を交互に配していくこと。
七十二候とは
二十四節気の各 1気を、さらに初候、二候、三候と3等分することで、1年を 72等分し、季節を節目を表した約 5日ごとに移り変わる暦のこと。
春
二十四節気
太陽が黄経 315度の点を通過するとき
冬至から約 45.66日後
正月節、1月14日~1月28日ごろ
2月4日ごろ
冬至と春分の中間にあたり、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合は、この日から立夏の前日までが春となる。
立春は、八十八夜、二百十日、二百二十日など、雑節の起算日*第 1日目となっている。
七十二候
とうふうこおりをとく
意味
東風*春風が冬の間張りつめていた氷を解かし始めるころ
時期
2月4日~2月8日ごろ
こうおうけんかんす
意味
ウグイスが鳴き始め、春の到来を告げるころ
時期
2月9日~2月13日ごろ
うおこおりにのぼる
意味
春の暖かさで湖や川の氷が割れた間から魚が飛び出てくるころ
時期
2月14日~2月18日ごろ
二十四節気
太陽が黄経 330度の点を通過するとき
冬至から約 60.87日後
正月中、1月19日~2月2日ごろ
2月19日ごろ
雨水の日に雛人形を飾りつけると「良縁」に恵まれるとされ、江戸時代からの風習として伝えられている。
七十二候
つちのしょううるおいおこる
意味
冷たい雪が解けて暖かい春の雨となり、大地に潤いをあたえるころ
時期
2月19日~2月23日ごろ
かすみはじめてたなびく
意味
霞*かすみがたなびき始めるころ
時期
2月24日~2月28日ごろ
そうもくきざしうごく
意味
やわらかな春の日差しの中、草木が芽吹き始めること
時期
3月1日~3月5日ごろ
二十四節気
太陽が黄経 345度の点を通過するとき
冬至から約 76.09日後
二月節、2月15日~2月29日ごろ
3月5日ごろ
七十二候
ちっちゅうこをひらく
意味
冬ごもりの虫たちが、暖かな春の日差しで大地が暖まり土から出てくるころ
時期
3月6日~3月10日ごろ
ももはじめてわらう
意味
桃のつぼみが開き、花が咲き始めるころ
時期
3月11日~3月15日ごろ
なむしちょうとなる
意味
さなぎから羽化した紋白蝶*もんしろちょうが羽ばたくころ
時期
3月16日~3月20日ごろ
二十四節気
太陽が黄経 0度の点*春分点を通過するとき
冬至から約 91.31日後
二月中、2月19日~3月4日ごろ
3月21日ごろ
七十二候
すずめはじめてすくう
意味
スズメが巣をつくり始めるころ
時期
3/21~3/25ごろ
さくらはじめてひらく
意味
桜の花が咲き始めるころ
時期
3/26~3/30ごろ
らいすなわちこえをはっす
意味
雷が遠くの空で鳴り始めるころ
時期
3/31~4/4ごろ
春
二十四節気
太陽が黄経 15度の点を通過するとき
冬至から約 106.53日後
三月節、3月5日~3月19日ごろ
4月5日ごろ
中国ではこの日を「清明節*せいめいせつ」と呼び、日本のお彼岸のように先祖の墓参りをする風習がある。
七十二候
げんちょういたる
意味
冬の間、暖かい東南アジアの島々で過ごしていたツバメが飛来するころ
時期
4/5~4/9ごろ
こうがんきたす
意味
雁*がんが北へ渡って行くころ
時期
4/10~4/14ごろ
にじはじめてあらわる
意味
鮮やかな虹が見え始める
時期
4/15~4/19ごろ
二十四節気
太陽が黄経 30度の点を通過するとき
冬至から約 121.75日後
三月中、3月20日~4月4日ごろ
4月20日ごろ
/ さまざまな穀物の生長を助ける意味がある。
七十二候
よしはじめてしょうず
意味
葦*よしが芽吹き始めるころ
時期
4/20~4/24ごろ
しもやんでなえいず
意味
霜が収まり稲の苗が育つころ
時期
4/25~4/29ごろ
ぼたんはなさく
意味
牡丹の花が咲き始めるころ
時期
4/30~5/4ごろ
夏
二十四節気
太陽が黄経 45度の点を通過するとき
冬至から約 136.97日後
四月節、3月17日~4月1日ごろ
5月5日ごろ
春分と夏至の中間で、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合、この日から立秋の前日までが夏となる。
七十二候
かえるはじめてなく
意味
蛙(かえる)が鳴き始めるころ
時期
5/5~5/9ごろ
きゅういんいずる
意味
冬眠していたミミズが地上に這い出てくるころ
時期
5/10~5/14ごろ
ちくかんしょうず
意味
筍(たけのこ)がひょっこりと顔を出すころ
時期
5/15~5/20ごろ
二十四節気
太陽が黄経 60度の点を通過するとき
冬至から約 152.18日後
四月中、4月2日~4月17日ごろ
5月20日ごろ
七十二候
かいこおこってくわをくらう
意味
蚕*かいこが盛んに桑の葉を食べ始めるころ
時期
5/21~5/25ごろ
こうさかう
意味
紅花が盛んに咲くころ
時期
5/26~5/30ごろ
ばくしゅういたる
意味
麦が熟して畑は黄金色に染まるころ
時期
5/31~6/5ごろ
二十四節気
太陽が黄経 75度の点を通過するとき
冬至から約 167.40日後
五月節、4月18日~5月3日ごろ
6月6日ごろ
/ 稲や麦などの穂先にある毛のような部分のある穀物類の種をまくころ。
七十二候
とうろうしょうず
意味
秋に生みつけられた卵から、カマキリが生まれるころ
時期
6/6~6/10ごろ
ふそうほたるとなる
意味
腐った草からホタルが現れるころ
時期
6/11~6/15ごろ
うめのみきなり
意味
梅の実が黄色く熟すころ
時期
6/16~6/20ごろ
二十四節気
太陽が黄経 90度の点を通過するとき
冬至から約 182.62日後
五月中、5月4日~5月19日ごろ
6月21日ごろ
七十二候
ないとうかるる
意味
夏枯草*うつぼぐさが枯れだすころ
時期
6/21~6/26ごろ
あやめはなさく
意味
アヤメが咲き始めるころ
時期
6/27~7/1ごろ
はんげしょうず
意味
烏柄杓*からすびしゃくが生え始めるころ
時期
7/2~7/6ごろ
二十四節気
太陽が黄経 105度の点を通過するとき
冬至から約 197.84日後
六月節、5月20日~6月5日ごろ
7月7日ごろ
七十二候
おんぷういたる
意味
温かい風が吹き始めるころ
時期
7/7~7/11ごろ
はすはじめてはなさく
意味
蓮*はすの花が咲き始めるころ
時期
7/12~7/16ごろ
たかすなわちがくしゅうす
意味
鷹*たかの雛が獲物の捕り方や飛び方を覚え、巣立ちの準備をするころ
時期
7/17~7/22ごろ
二十四節気
太陽が黄経 120度の点を通過するとき
冬至から約 213.06日後
六月中、6月6日~6月21日ごろ
7月23日ごろ
七十二候
きりはじめてはなをむすぶ
意味
桐の花が蕾をつけるころ
時期
7/23~7/27ごろ
つちうるおいてむしあつし
意味
土が湿り蒸し暑くなるころ
時期
7/28~8/1ごろ
たいうときどきおこなう
意味
夕立や台風などの夏の雨が、時として激しく降るころ
時期
8/2~8/6ごろ
秋
二十四節気
太陽が黄経 135度の点*秋分点を通過するとき
冬至から約 228.28日後
七月節、6月22日~7月7日ごろ
8月7日ごろ
七十二候
りょうふういたる
意味
夏の暑い風が和らぎ、涼しい風に替わり始めるころ
時期
8/7~8/12ごろ
かんせんなく
意味
夏の終わりを告げるかのように、ヒグラシが鳴き始めるころ
時期
8/13~8/17ごろ
ふかききりまとう
意味
濃い霧が立ち込め始めるころ
時期
8/18~8/22ごろ
二十四節気
太陽が黄経 150度の点を通過するとき
冬至から約 243.4906日後
七月中、7月8日~7月23日ごろ
8月23日ごろ
七十二候
めんぷひらく
意味
綿を包む萼*がくが開き始めるころ
時期
8/23~8/27ごろ
てんちはじめてしゅくす
意味
ようやく暑さが鎮まるころ
時期
8/28~9/1ごろ
こくものすなわちのぼる
意味
稲が実るころ
時期
9/2~9/7ごろ
二十四節気
太陽が黄経 165度の点を通過するとき
冬至から約 258.71日後
八月節、7月24日~8月8日ごろ
9月8日ごろ
七十二候
そうろしろし
意味
草花の上に降りた朝露が白く光るころ
時期
9/8~9/12ごろ
せきれいなく
意味
セキレイが鳴き始めるころ
時期
9/13~9/17ごろ
げんちょうさる
意味
暖かくなる春先に日本にやってきたツバメが、暖かい南の地域へと帰っていくころ
時期
9/18~9/22ごろ
二十四節気
太陽が黄経180度の点*秋分点を通過するとき
冬至から約 273.93日後
八月中、8月28日~9月12日ごろ
9月23日ごろ
七十二候
らいすなわちこえをおさむ
意味
雷鳴が聞こえなくなるころ
時期
9/23~9/27ごろ
ちゅっちゅうこをはいす
意味
土の中に住む虫たちが、冬ごもりの支度をはじめるころ
時期
9/28~10/2ごろ
みずはじめてかる
意味
田畑の水を干し始め、稲穂の刈り入れを始めるころ
時期
10/3~10/7ごろ
二十四節気
太陽が黄経 195度の点を通過するとき
冬至から約 289.15日後
九月節、9月13日~9月27日ごろ
10月8日ごろ
七十二候
こうがんきたる
意味
雁*がんが飛来し始めるころ
時期
10/8~10/12ごろ
きくはなひらく
意味
菊の花が咲き始めるころ
時期
10/13~10/17ごろ
しっそくこにあり
意味
キリギリスが戸口で鳴き始めるころ
時期
10/18~10/22ごろ
二十四節気
太陽が黄経 210度の点を通過するとき
冬至から約 304.37日後
九月中、9月28日~10月13日ごろ
10月24日ごろ
七十二候
しもはじめてふる
意味
霜が降り始めるころ
時期
10/23~10/27ごろ
しぐれときどきほどこす
意味
小雨がしとしと降り始めるころ
時期
10/28~11/1ごろ
ふうかつきなり
意味
モミジやツタが色づいてくるころ
時期
11/2~11/6ごろ
冬
二十四節気
太陽が黄経 225度の点を通過するとき
冬至から約 319.59日後
十月節、10月14日~10月28日ごろ
11月7日ごろ
七十二候
つばきはじめてひらく
意味
山茶花*さざんかの花が咲き始めるころ
時期
11/7~11/11ごろ
ちはじめてこおる
意味
大地が凍り始めるころ
時期
11/12~11/16ごろ
きんせんかさく
意味
水仙の花が咲き始めるころ
時期
11/17~11/21ごろ
二十四節気
太陽が黄経 240度の点を通過するとき
冬至から約 334.81日後
十月中、10月内
11月22日ごろ
七十二候
にじかくれてみえず
意味
陽射しが弱まり、虹を見かけなくなるころ
時期
11/22~11/27ごろ
さくふうはをはらふ
意味
冷たい北風が、木々の葉を落とすころ
時期
11/28~12/2ごろ
たちばなはじめてきなり
意味
橘*たちばなの実が黄色く色づき始めるころ
時期
12/3~12/6ごろ
二十四節気
太陽が黄経 255度の点を通過するとき
冬至から約 350.02日後
十一月節、11月14日~11月28日ごろ
12月7日ごろ
七十二候
へいそくしてふゆとなる
意味
天と地が寒がり真冬になるころ
時期
12/7~12/11ごろ
くまあなにちっす
意味
熊が冬眠のために穴に篭るころ
時期
12/12~12/15ごろ
けつぎょむらがる
意味
鮭が群がり川を上るころ
時期
12/16~12/21ごろ
二十四節気
太陽が黄経 270度の点を通過するとき
冬至から 0日後
十一月中、11月29日~12月14日ごろ
12月21日ごろ
七十二候
ないとうしょうず
意味
夏枯草*うつぼぐさが芽を出すころ
時期
1/6~9ごろ
びかくげす
意味
ヘラジカが角を落とし生え変わるころ
時期
1/6~9ごろ
せつかむぎをいだす
意味
降り積もった雪の下で、麦が芽を出し始めるころ
時期
1/6~9ごろ
二十四節気
太陽が黄経 285度の点を通過するとき
冬至から約 15.22日後
十二月節、12月15日~12月28日ごろ
1月5日ごろ
七十二候
せりすなわちさかう
意味
芹*せりがよく育つころ
時期
12/22~12/26ごろ
すいせんうごく
意味
地中で凍った泉の水が溶けて動き始めるころ
時期
12/27~12/31ごろ
きじはじめてなく
意味
オスのキジが鳴き始めるころ
時期
1/1~1/5ごろ
二十四節気
太陽が黄経 300度の点を通過するとき
冬至から約 30.44日後
十二月中、12月29日~1月13日ごろ
1月21日ごろ
七十二候
かんとうはなさく
意味
蕗の薹*ふきのとうの蕾が咲き始めるころ
時期
1/6~1/9ごろ
さわみずこおりつめる
意味
沢の水が氷となり、厚く張りつめるころ
時期
1/25~1/29ごろ
にわとりはじめてにゅうす
意味
ニワトリが卵を産み始めるころ
時期
1/30~2/3ごろ